後期高齢者医療制度
後期高齢者医療被保険者証の新規交付終了について
国から示されたマイナンバーカードと被保険者証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の紙の被保険者証は交付できなくなります(紛失等による再交付を含む)。
ただし、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、内容に変更がない限り、記載された有効期限まで使用できます。
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、被保険者証の記載内容に変更が生じた方及び被保険者証を紛失等された方には、令和8年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、今までと同じように医療を受けることができます。
※被保険者証の紛失等による交付には申請が必要です。
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 65歳~74歳で一定の障害(※)があり、申請により広域連合の認定を受けた方
※)身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、精神障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、国民年金法等における障害年金1級・2級
保険料について
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
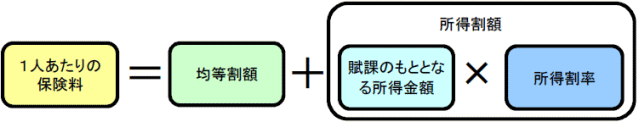
保険料率(令和7年度)
- 均等割額=54,428円/年額 所得割率=11.04%
- 1人あたりの保険料の上限額80万円
- 保険料率は2年ごとに見直され、和歌山県内では均一
賦課のもととなる所得金額
前年の所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です。雑損失の繰越控除分は控除されません。
保険料の納付方法
原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、次に該当する方は普通徴収となります。特別徴収、普通徴収の判定は、年金額などにより自動的に行われます。
- 年間の年金受給額が18万円未満の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方
- 年度の途中で資格を取得された方
- 当町へ年金天引き中止の申請をされた方
特別徴収
年金から保険料の天引きを行います。前年の所得が確定するまでの4・6・8月は、前年度2月の保険料額を天引きします。
普通徴収
納付書や口座振替による納付方法です。前年の所得が確定後に、年間保険料額を9回に分けて納めていただきます(7月~翌年3月まで)。口座振替による納付をご希望の方は、かつらぎ町公金取扱いの金融機関へ届出が必要です。
- 和歌山県農業協同組合
- 株式会社紀陽銀行
- 株式会社南都銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 株式会社ゆうちょ銀行(近畿2府4県に所在する各ゆうちょ銀行・郵便局に限る)
保険料の軽減制度
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
|
軽減割合 |
所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
|---|---|
| 令和7年度 | |
| 7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+30.5万円×(被保険者数)以下 |
| 2割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+56万円×(被保険者数)以下 |
- 65歳以上の公的年金を受給されている方は、軽減の判定時に15万円が控除されます。
- 軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
被用者保険の被扶養者にかかる軽減
後期高齢者医療制度加入の前日が被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額がかかりません。
保険料の減免制度
災害などにより著しい損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な場合は、これを減免する制度があります。
医療の給付
窓口での自己負担割合
医療費の自己負担割合は所得に応じて決まります。
| 区分 | 負担割合 | 該当要件 |
|---|---|---|
|
現役並み Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
3割 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者は以下のようになります。
ただし、被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合383万円未満の方は、お住まいの市町村の担当窓口に申請することにより「1割」または「2割」負担になります。 *現役並み所得の被保険者(世帯にほかの被保険者がいない場合に限る)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満の方も、申請により「1割」または「2割」負担になります。 |
| 一般Ⅱ | 2割 | 住民税の課税所得額が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合は320万円)以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 |
| 一般Ⅰ |
1割 |
現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方 |
| 区分Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の方(うち区分Ⅰ以外の方) | |
| 区分Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・ 控除(年金の所得は控除額80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方および老齢福祉年金受給者 |
医療費が高額になったとき
1か月(同月内)にかかった保険適用となる医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
| 現役並み 所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>(※) |
|
| 現役並み 所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>(※) |
|
| 現役並み 所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>(※) |
|
|
一般Ⅰ・Ⅱ |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 <44,400円>(※) |
| 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(※) 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が< >内の額となります。
入院したときの食事代
| 区分 | 1食あたり負担額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者および一般Ⅰ・Ⅱ |
510円 |
|
| 区分Ⅱ | 90日までの入院 |
240円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
190円 |
|
| 区分Ⅰ |
110円 |
|
高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度における世帯内で、医療費と介護サービス利用料の合計額が一定の金額を超える場合、定められた限度額を超えた分が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
年間の限度額(対象期間:毎年8月~翌年7月末)
| 所得区分 | 合算後の限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
| 区分Ⅱ | 31万円 |
| 区分Ⅰ | 19万円 |
申請により費用が支給される場合
- 医師の指示によりコルセットなどの補装具をつくったとき
- 旅行中などに、急病等でやむをえずマイナ保険証・資格確認書等を持たずに医療機関を受診したとき
- 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
- 区分Ⅰ・Ⅱに該当する方が、医療機関に入院し、区分の適用を受けずに食事代を支払ったとき
- 被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき(葬祭費の支給)
※上記1から4の申請には、領収書等が必要です。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。 ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。示談の前に必ず後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。
後期高齢者医療制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページ![]() もご覧ください。
もご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康保険課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする![]()
